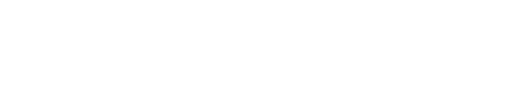KEYWORDS
栄養 | 小山市でダイエットに強いBODY UP DATE
-
BLOG2025.08.24
脂肪燃焼を効率よくする食事法
 こんにちは。
こんにちは。
本日は脂肪燃焼を効率よくするための食事法についてお話しようと思います。伝えたい実践ポイント
脂肪を落としたいと考えたとき、まず浮かぶのは「運動」ですが、実際には食事のコントロールこそが鍵です。
トレーニングで消費できるカロリーは限られていますが、食事での調整は日常的に大きな影響を与えます。
1. タンパク質をしっかり確保する
脂肪を減らしつつ筋肉を守るには、体重1kgあたり1.6〜2.0gのタンパク質が目安。
鶏胸肉、魚、卵、大豆食品、プロテインパウダーなどをバランスよく取り入れることが重要です。👉 筋肉が減ると基礎代謝が落ちて脂肪燃焼効率も悪くなるので、タンパク質は最優先すべき栄養素です。
2. 炭水化物は「質」と「タイミング」で調整
糖質を完全に抜く必要はありません。
むしろ、活動量に合わせて摂取した方が代謝が落ちにくいです。
-
朝・トレーニング前後 → 白米やオートミールなど消化の良い炭水化物
-
夜や活動量が少ない日 → 玄米、さつまいも、野菜など低GIの炭水化物
👉 「使うときに補給する」というイメージを持ちましょう。
3. 良質な脂質を味方にする
脂肪燃焼の妨げになるのは「揚げ物や加工食品に含まれるトランス脂肪酸」。
逆に、オメガ3脂肪酸(青魚・亜麻仁油・チアシード)やオリーブオイルは代謝を助け、ホルモンバランスも整えます。👉 ダイエット中も脂質はゼロにせず、1日の総カロリーの20〜30%を目安に取り入れましょう。
4. 野菜と食物繊維を十分に
食物繊維は血糖値の急上昇を抑え、腸内環境を整えます。
特に**水溶性食物繊維(わかめ・大麦・りんごなど)は脂質の吸収を抑える効果も。👉 毎食に「手のひらサイズの野菜」を意識するとバランスが取りやすいです。
5. 水分補給を怠らない
水分不足は代謝を下げ、脂肪燃焼に必要な酵素の働きも鈍らせます。
目安は体重×30〜40ml。緑茶やブラックコーヒーはカフェイン効果で脂肪燃焼を助けますが、飲みすぎには注意。6. 食事の間隔と血糖コントロール
空腹が長すぎると筋肉が分解されやすくなり、逆効果。
3〜4時間ごとに小分けで栄養を入れることで、血糖値の安定と脂肪燃焼の持続が狙えます。7. トレーニング前後の栄養戦略
トレーニング前:バナナやおにぎりなどで軽く糖質を補給
トレーニング後:30分以内にプロテイン+炭水化物を摂ると回復と筋肉合成がスムーズ👉 この「ゴールデンタイム」を逃さないことで、体は脂肪をためにくくなります。
脂肪燃焼を効率よく進めるには、ただ「食べない」のではなく、筋肉を守りながら代謝を高める食事が必要です。
ポイントは以下の通りです↓-
〇タンパク質は十分に
-
〇炭水化物は質とタイミングで調整
-
〇良質な脂質を取り入れる
-
〇野菜・水分を欠かさない
-
〇トレーニング前後の栄養戦略
ダイエットは「我慢」ではなく「戦略」で十分に戦えます。
正しい食事を味方につければ、脂肪は効率よく燃えていきますので、是非皆さんもやってみて下さい💪
6 -
-
BLOG2020.08.27
ミネラルについて
-
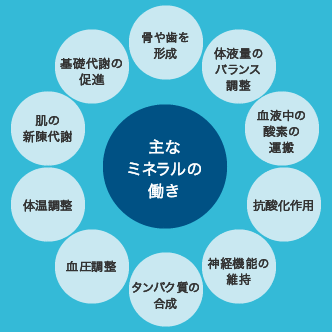
今日はミネラルについてお話します。
ミネラルとは、次の3つの形で生体内に存在し、その役割を果たします。
①難溶性の無機塩として骨や歯の構成成分となる。
②イオンとして生体反応の調節をする。
③有機化合物と結合し重要な物質の構成成分となる。ミネラルの働きを一つずつ紹介します。
・カルシウム(Ca)
生体内に最も多量に存在し、99%が骨や歯に、約1%が細胞内に、約0.1%が血液中に存在している。
骨や歯を形成したり、筋肉の収縮、神経興奮の伝導などの働きがある。・リン(P)
カルシウムに次いで多いミネラルであり、生体内の全ての組織と細胞に存在し、体重の約1%を占める。
約80%が骨や歯に含まれ、硬組織や細胞膜の構成成分で、高エネルギーリン酸化合物、ビタミンからの補酵素の構成元素としてなど広く関与している。・マグネシウム(Mg)
生体内で60~65%は骨中に、27%は筋肉中に含まれ、全ての細胞内にマグネシウムイオンが存在する。
酸素の活性化や体温調節、神経の興奮や筋肉の収縮、副甲状腺ホルモンの分泌、脂質代謝の改善など多くの働きがある。・カリウム(K)
細胞内に98%、細胞外に2%存在し、細胞内に最も多い陽イオン。
細胞内の浸透圧・PH調整、膜輸送、筋肉の収縮、酵素の活性化などの働きがある。・ナトリウム(Na)
細胞外液に50%、骨中に40%、細胞内液に10%存在する陽イオンで、大部分が塩化ナトリウムとして摂取される。
浸透圧、細胞間液量やPHの調整、細胞内外の電位差の維持、グルコースやアミノ酸の吸収における能動輸送、筋肉収縮促進などの働きがある。・塩素(Cl)
約70%が細胞外液に、30%が細胞内液に塩素イオンとして存在し、細胞外液の約60%を占める。
胃酸の構成成分で浸透圧、細胞間液量やPHの調整などの働きがある。・鉄(Fe)
成人体内に3~4%存在し、ヘモグロビン鉄、ミオグロビン鉄、貯蔵鉄、酵素鉄、血清鉄の5つに分類され、この5つの働きの後、体の一部になったり排出されるほか、リサイクルされ再び利用される。・銅(Cu)
生体内に約80~100mg含まれ、骨、筋肉、肝臓に存在する。
ヘモグロビンの合成に必要であり、チトクローム酸化酵素、チロシナーゼなどの酵素の構成成分。・亜鉛(Zn)
体内に約2g含まれ、皮膚、血液、筋肉、肝臓など広く分布している。
200以上の酵素の構成成分で、成長、免疫系、味覚などの感覚、皮膚、骨の機能維持に関与するほか、皮膚たんぱく質やコラーゲンの生合成にも不可欠である。・セレン(Se)
成人体内に約13mg含まれ、脂肪酸の過酸化防止に役立つグルタチオンパーオキシダーゼの構成成分。・クロム(Cr)
成人体内に約2g含まれ、糖、脂質、たんぱく質の代謝や結合組織の代謝に関与するほか、免疫反応の改善にも不可欠。
特に糖質をグリコーゲンに変えるインスリンの補助因子となる。(インスリン作用の増強)・ヨウ素(I)
成人体内に約15mg含まれ、70~80%が甲状腺に存在する。
甲状腺ホルモンの構成成分としてエネルギー代謝やたんぱく質合成に関与する。・コバルト(Co)
成人体内に約2mg含まれ、ビタミンB12の構成成分、赤血球の形成に関与している。・マンガン(Mg)
成人体内に約15mg含まれ、25%が骨中に、次いで肝臓、脾臓、腎臓に存在する。
アルギナーゼなどの酵素の構成成分であり、酵素反応を活性化させる補助因子としての機能もある。・硫黄(S)
大部分は含硫アミノ酸としてたんぱく質に含まれる。
硫黄のSH基には生体の解毒や酵素の活性調節機能がある。・モリブデン(Mo)
肝臓中に多く含まれ、キサンチンオキシダーゼなどの酵素の構成成分。・フッ素(F)
約95%が歯や骨に含まれる。
歯の石灰化の促進、口内の細菌や、これが生産する酵素活性抑制などに関与。歯のう蝕予防なども担っている。以上、ミネラルは多いので過剰摂取や欠乏症については次回書きます。
1 -